身長211cmの女子との出会い
彼女との出会いは、まるで映画のワンシーンのようだった。秋の夕暮れ、オレンジ色の光が差し込む公園で、僕はいつものようにジョギングをしていた。その日もいつものコースを走りながら、心地よい風と共にリラックスしていた。しかし、目の前に現れたその瞬間、全てが変わった。
突然、僕の視界に入ったのは、他の何よりも異彩を放つ存在だった。身長211cmの彼女が、まるで巨人のように立っていたのだ。その長い脚と圧倒的な体躯は、自然と目を引く。彼女はスポーツウェアを身にまとい、長い髪を一つにまとめていた。彼女の姿を見た瞬間、僕の足が止まった。
彼女はただ立っているだけではなく、僕に向かって微笑んでいた。その笑顔には、どこか神秘的な魅力があった。僕は、その微笑みに引き寄せられるように、自然と彼女の元へと足を進めた。近づくにつれて、その巨体がますます圧倒的に感じられた。彼女は、普通の人とは全く異なるオーラを纏っていた。
「こんにちは、ジョギングを楽しんでいるみたいですね。」彼女は柔らかい声で話しかけてきた。その声は、彼女の体格とは対照的に、非常に落ち着いていて優しかった。僕は、突然のことに少し戸惑いながらも、彼女の親しみやすさに心を和ませた。
「こんにちは。ええ、ここはいつも走っているコースなんです。」僕は少し緊張しながらも、なんとか返事をした。彼女は軽くうなずき、再び微笑んだ。
「私もここでよくランニングをしているんです。でも、こんなに背が高いから、目立ってしまって…。それで、なかなか友達ができなくて。」彼女の言葉には、少しの寂しさが含まれていた。彼女の背の高さが、彼女にとっての障壁になっていることが伝わってきた。
「そんなことないですよ。あなたの背の高さは素晴らしいですし、きっとたくさんの人があなたと友達になりたいと思っているはずです。」僕は少しでも彼女の気持ちを軽くするために、そう言った。彼女は驚いたような顔をして、しばらく黙っていたが、やがて再び笑顔を見せた。
「ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいです。」彼女の笑顔には、本当に心からの感謝の気持ちが込められているように感じられた。その瞬間、僕たちの間に不思議な絆が生まれたように思えた。
その後、僕たちはしばらくの間、一緒にジョギングをすることにした。彼女のペースは思ったよりも速く、僕はついていくのに必死だった。しかし、彼女と一緒に走ることが楽しく、時間が経つのを忘れてしまった。彼女の存在は、僕に新たな刺激を与えてくれた。
こうして、身長211cmの女子との出会いは、僕の人生において忘れられない出来事となった。この日をきっかけに、僕たちの間には深い友情が芽生えることになるのだった。

予期せぬ接近
彼女とのジョギングを楽しんだ翌日から、僕の日常は一変した。翌朝、いつもの時間に公園に向かうと、彼女がすでにベンチに座って待っていたのだ。彼女は僕を見つけると、大きな手を振って微笑んだ。その笑顔は昨日と同じで、まるで太陽のように輝いていた。
「おはよう、今日も一緒に走ろうね。」彼女の言葉は自然で、僕も自然とその提案を受け入れた。こうして、僕たちのジョギングセッションが始まった。彼女の足取りは軽やかで、まるで大きな体が空気を切り裂いて進むかのようだった。僕はその背中を見ながら、彼女の強さと美しさに改めて感嘆した。
数日が過ぎると、彼女とのジョギングは僕の日課となり、彼女がいないと物足りなさを感じるようになった。彼女も同じ気持ちだったのか、毎朝必ず公園で待っていてくれた。僕たちの距離は次第に縮まり、ただのジョギング仲間から、少しずつ友人へと変わっていった。
ある日、いつものようにジョギングを終えた後、彼女が僕に話しかけた。「今日はちょっと話したいことがあるの。」その言葉に驚いたが、僕は彼女の真剣な表情を見て、黙ってうなずいた。彼女は深呼吸をしてから話し始めた。
「実は、私、昔から背が高いことがコンプレックスだったの。小さい頃から周りと違って、いつも注目を浴びてしまって…。それが嫌で、自分を隠すようになったの。でも、君と出会ってから、その気持ちが少しずつ変わり始めたの。」彼女の言葉には、これまでの苦労と孤独がにじみ出ていた。
「君は私を普通に接してくれるし、一緒にいると自分が特別じゃないって思えるんだ。だから、ありがとう。本当に感謝しているの。」彼女の目には涙が浮かんでいた。僕はその言葉にどう答えればいいのか分からず、ただ彼女の手を握った。
「僕も、君と出会えて良かったよ。君のおかげで、毎日が楽しくなった。だから、これからも一緒に走ろう。」僕の言葉に、彼女は微笑んでうなずいた。僕たちの間には、言葉にできない絆が確かに存在していた。
その日以降、彼女との関係はさらに深まっていった。僕たちはジョギングだけでなく、一緒に食事をしたり、映画を観たりするようになった。彼女は僕にとって、特別な存在になっていった。しかし、そんな日々が続く中で、僕たちの関係に影を落とす出来事が起こることになる。
それは、彼女が突然、僕に距離を置き始めたことだった。何が原因なのか分からず、僕は困惑した。彼女は理由を話そうとせず、ただ「少し時間が欲しい」とだけ言った。その言葉に、僕は何も言えず、ただ彼女の言葉を信じるしかなかった。
予期せぬ接近から始まった僕たちの関係は、一時的に停滞することになった。僕は彼女が戻ってくるのを信じ、待つことにした。しかし、その間に僕は、彼女の気持ちをもっと理解しようと心に決めたのだった。
逃げ場のない対峙
彼女との距離が急に広がったことで、僕の日常は再び孤独なものになった。彼女がいないジョギングは味気なく、公園もどこか冷たく感じられた。彼女が求めた「少しの時間」がどれだけ続くのか、僕には見当もつかなかった。しかし、僕は彼女が戻ってくることを信じて、毎日公園に通い続けた。
ある日の夕方、いつも通りジョギングをしていた僕は、ふと公園のベンチに座っている彼女の姿を見つけた。彼女はうつむき加減で、どこか疲れたような表情をしていた。僕は迷うことなく彼女の元へ駆け寄った。
「やあ、久しぶりだね。どうしたんだい?」僕はできるだけ明るく声をかけたが、彼女の表情は変わらなかった。彼女はしばらく沈黙した後、重い口を開いた。
「ごめんね、突然距離を置いてしまって…。でも、今日はどうしても話さなきゃいけないことがあるの。」彼女の言葉には決意が感じられた。僕はその言葉に真剣に耳を傾けた。
「実は、私には昔からの夢があるの。プロバスケットボール選手になること。だけど、その夢を追いかけるために、遠くの街に引っ越さなきゃいけないの。」彼女の言葉に、僕は一瞬言葉を失った。彼女がそんな大きな夢を抱えていたことを、僕は知らなかった。
「だから、君と距離を置いたのは、その決断をするためだったの。本当はずっと一緒にいたかったけど、夢を追いかけるためには、君との関係が重荷になってしまうかもしれないって思ったの。」彼女の言葉には、深い苦悩がにじみ出ていた。
「そんなことないよ。君の夢を応援したい。遠くに行くことがあっても、僕たちはきっと繋がっていられるよ。」僕は必死に彼女を励まそうとした。しかし、彼女の目には涙が浮かんでいた。
「ありがとう。でも、今は自分の夢に集中したいの。君のことは大切だけど、今は自分を優先させなきゃいけないの。」彼女の決意は固く、僕には何も言えなかった。僕たちはしばらくの間、黙ってベンチに座っていた。お互いに何も言わず、ただ静かに時間が過ぎるのを感じていた。
「わかったよ。君の夢を応援するよ。いつかまた会えると信じてる。」僕はようやく言葉を絞り出した。彼女はうなずき、涙を拭った。
「ありがとう。君に出会えて、本当に良かった。」彼女はそう言って、立ち上がった。その背中は、初めて会った時のように大きく、そして強く感じられた。
僕は彼女を見送りながら、心の中で彼女の成功を祈った。そして、彼女がいない公園でのジョギングを再び始めた。彼女との思い出が、僕を支えてくれると信じていたから。
彼女との別れは辛かったが、彼女の夢を知り、その夢を応援することができたことに感謝していた。逃げ場のない対峙を経て、僕たちはそれぞれの道を歩むことになったが、その道の先にはきっとまた再会の機会があると信じている。
絶望の頂点
彼女が去った後、僕の心には大きな穴が空いたようだった。毎朝のジョギングは孤独なものとなり、彼女との思い出が鮮明に蘇る度に、胸が痛んだ。彼女が遠くの街で夢を追いかけていることを知っていても、その事実は僕の孤独を癒してはくれなかった。
数ヶ月が経ち、僕の生活は少しずつ元に戻りつつあった。仕事に没頭し、新しい趣味を見つけようと試みたが、彼女の存在は常に心の片隅にあった。彼女の笑顔、彼女との会話、そして彼女と共に過ごした時間は、忘れられるものではなかった。
ある日、彼女から一通の手紙が届いた。手紙には彼女の近況が綴られていた。新しい街での生活、プロバスケットボールチームでのトレーニング、そして新しい友達との関わり。彼女が順調に夢に向かって進んでいることを知り、僕は嬉しく思った。しかし、手紙の最後には、予想もしなかった言葉が書かれていた。
「でも、本当のことを言うと、君がいないことが寂しいんだ。」
その言葉は、僕の心に深く突き刺さった。彼女も僕と同じように孤独を感じているという事実が、僕の中に混乱と絶望を呼び起こした。僕は彼女に返事を書くべきか、会いに行くべきか、何をするべきか全くわからなかった。
その夜、僕は眠れずにベッドの中で考え続けた。彼女の夢を応援するために、僕は彼女を送り出した。しかし、その決断が本当に正しかったのか、自問自答した。彼女も僕と同じように孤独を感じているならば、僕たちの距離は本当に必要だったのか。
次の日、僕は手紙に返事を書くことに決めた。手紙には、僕の気持ちを正直に綴った。彼女がいなくなってからの孤独な日々、彼女を思い続けていること、そして彼女が戻ってきてくれることをどれほど望んでいるかを、全て書いた。そして、最後に一言付け加えた。
「君が幸せであることが一番大切だ。でも、もし君が戻ってきたいと思うなら、僕はいつでも待っている。」
手紙を送り出した後、僕は彼女からの返事を待ち続けた。日々の生活は続いていたが、心の中には常に彼女のことがあった。彼女の返事が来ることを祈りながら、僕は再びジョギングを始めた。彼女との思い出の場所で、彼女との再会を夢見て走り続けた。
数週間後、彼女からの手紙が再び届いた。手紙を開く手が震え、胸が高鳴った。手紙には、彼女の決意が書かれていた。
「私は自分の夢を追いかけるためにここに来た。でも、君と一緒にいることが私の本当の幸せだと気づいた。だから、戻ることに決めた。もう一度、君と一緒に走りたい。」
その言葉に、僕は涙が溢れた。彼女が戻ってくるという事実が、僕にとって最高の喜びだった。僕たちは再び一緒に走ることができる。彼女との再会を夢見て、僕はその日も公園を走り続けた。絶望の頂点から、僕たちは再び希望を見つけることができたのだった。
意外な結末と新たな絆
彼女が戻るという知らせは、僕にとってこの上ない喜びだった。手紙を読んだ翌日、僕は彼女を迎えるために最善の準備を始めた。再会の場所は、初めて出会った公園。あのオレンジ色の夕暮れが再び僕たちを迎えてくれることを願って。
その日がやってきた。彼女の到着時間が近づくにつれ、僕の胸は高鳴り、緊張と興奮が入り混じった感情が溢れていた。公園のベンチに座りながら、何度も時計を確認した。やがて、遠くから見覚えのある大きなシルエットが近づいてくるのが見えた。
彼女だ。彼女は変わらない笑顔で、まっすぐに僕の方に歩いてきた。僕は立ち上がり、彼女に向かって手を振った。彼女が近づくと、その巨体が以前よりも少し頼もしく見えた。
「久しぶり、元気だった?」彼女は少し照れくさそうに尋ねた。その声を聞くだけで、僕の心は温かくなった。
「元気だよ。君も元気そうで何よりだ。」僕は微笑み返した。お互いの顔を見つめながら、自然と手を取り合った。その瞬間、時間が止まったように感じた。
僕たちはその後、ゆっくりと公園を歩きながら、お互いの近況を話し合った。彼女はプロバスケットボールチームでの経験や新しい友人たちについて語り、僕も仕事や趣味について話した。話は尽きることがなく、気がつけば夕暮れ時になっていた。
「ここでまた一緒に走れるなんて、本当に嬉しいよ。」彼女は感慨深げに言った。僕も同じ気持ちだった。僕たちは再びジョギングを始め、初めて会った頃のように並んで走った。その時間は、まるで魔法のように感じられた。
彼女が戻ってきたことで、僕たちの絆は以前よりも強くなった。彼女の夢を応援するために離れた日々は、お互いにとって必要な時間だったのだと気づいた。彼女は再びプロバスケットボール選手になることを目指しつつ、僕との時間も大切にしてくれた。
ある日、彼女がふと僕に尋ねた。「ねえ、これからのこと、どう思ってる?」その質問には、僕たちの未来がかかっているように感じた。
「僕は君と一緒にいることが一番幸せだよ。君の夢も応援するし、僕たちの時間も大切にしたい。」僕は心からそう答えた。彼女は微笑み、僕の手を握りしめた。
「ありがとう。君と一緒にいることで、私はもっと強くなれる気がする。これからもよろしくね。」彼女の言葉に、僕の心はさらに温かくなった。
その後、僕たちは新しい目標を立てた。彼女がプロバスケットボール選手として成功するために、僕もサポートを惜しまないこと。そして、お互いの夢を尊重し合いながら、一緒に成長していくことを誓った。
彼女との出会いから始まった僕たちの物語は、意外な結末を迎え、そして新たな絆を築くことができた。これからも続くであろう僕たちの冒険に、胸を躍らせながら、僕たちは共に未来を歩んでいく。
意外な結末と新たな絆。僕たちの物語はまだ始まったばかりだ。この先に待つ新たな挑戦と喜びを楽しみにしながら、僕たちは共に歩み続けることを決意したのだった。

ゲームばかりでモテない人生だった主人公
しかしそんなゲームのコミュティで知り合った女性に親切に
攻略を教え腕前を上げさせる事に成功
そうして感謝され会ってお祝いする事に。
ドキドキしながら待っていたら、現れたのは211cmの地雷系女子だった。
とてつもなく大きいけれど可愛いその子にドキドキしながらお祝いの乾杯をしたら
飲み過ぎて記憶を無くす…そして隣を見たらまるで事後のような…
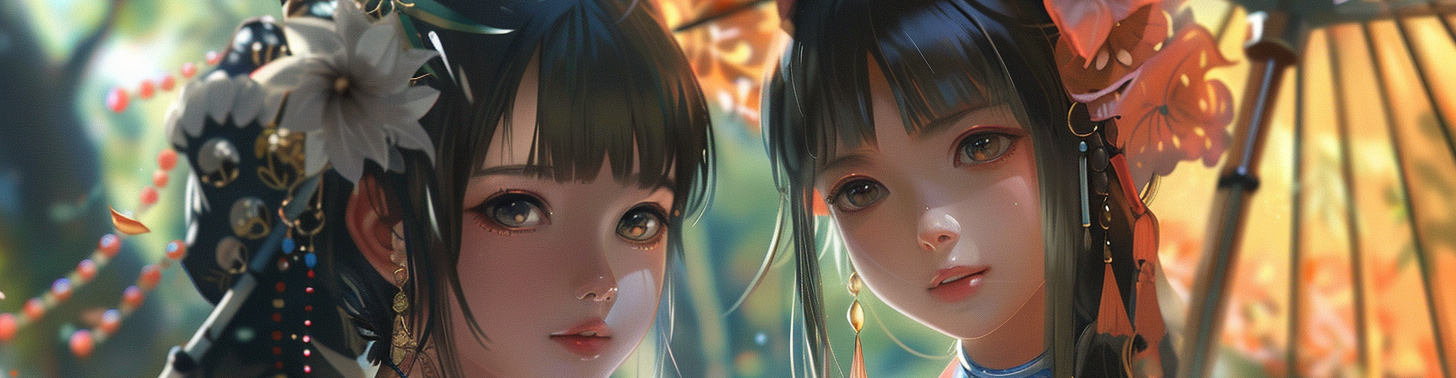


コメント