吉浦さんの誘い
須波くんは、放課後の教室で一人静かに読書を楽しんでいた。そのとき、クラスメイトの吉浦さんが彼の席に近づいてきた。吉浦さんは、明るくて社交的な性格で、クラスの中心的存在だった。須波くんとはあまり話す機会がなかったが、今日は何か特別な用事があるらしい。
「須波くん、ちょっといい?」吉浦さんが微笑みながら話しかけた。
「え?あ、うん、どうしたの?」須波くんは驚きつつも返事をした。
「実はね、文芸部に入ってみないかと思って。須波くん、本を読むのが好きそうだし、きっと楽しめると思うんだ。」
文芸部という言葉に、須波くんの心は少し揺れた。確かに、本を読むのは好きだが、部活動に参加するなんて考えたこともなかった。人前で発表することも苦手で、静かな時間を過ごすのが好きだったからだ。
「でも、僕、人前で発表するのはちょっと苦手で…」須波くんは遠慮がちに答えた。
「大丈夫だよ。文芸部には、いろんな個性の人がいるし、発表が苦手な人もいる。でも、みんなで作品を共有したり、意見を出し合ったりするのはとても楽しいよ。それに、須波くんの書く文章、きっとみんな喜ぶと思うんだ。」
吉浦さんの言葉には、どこか温かみがあった。須波くんは、自分の内向的な性格を変えるチャンスかもしれないと思った。そして、何よりも吉浦さんの誘いを断るのは申し訳ない気がした。
「うーん、わかった。じゃあ、試しに入ってみるよ。」須波くんは決意したように答えた。
「本当?やったー!文芸部にようこそ!」吉浦さんは嬉しそうに須波くんの手を握った。
その日の放課後、須波くんは吉浦さんと一緒に文芸部の部室へ向かった。部室は校舎の一番奥にあり、静かな場所だった。部室の扉を開けると、数名の部員たちが思い思いの場所で読書をしたり、執筆をしていたりするのが目に入った。
「みんな、今日は新しい仲間を紹介するよ!須波くんだよ。」吉浦さんが元気よく紹介すると、部員たちは一斉に顔を上げ、笑顔で須波くんを迎えた。
「初めまして、須波です。よろしくお願いします。」須波くんは緊張しながらも、丁寧に挨拶をした。
「ようこそ、須波くん。ここでは、自分の好きなことを自由にやっていいんだよ。リラックスしてね。」と、部長の安登先輩が優しく声をかけた。
安登先輩は、長身で知的な雰囲気を持った人物だった。彼の穏やかな言葉に、須波くんは少し緊張がほぐれた。
部室の一角には、たくさんの本が並んでいる書棚があり、その前には大きなテーブルが置かれていた。須波くんはその光景を見て、ここが自分の新しい居場所になるかもしれないと感じた。
「今日は初めてだから、特に何もせずに、自由に過ごしていいよ。質問があれば何でも聞いてね。」吉浦さんがそう言うと、須波くんは頷いた。
しばらくして、須波くんは書棚から一冊の本を手に取り、テーブルの一角に座った。周りの部員たちもそれぞれの活動を続けており、静かで落ち着いた雰囲気が漂っていた。
この静かな空間で、須波くんは自分の内面と向き合い、新しい一歩を踏み出す準備ができたように感じた。文芸部での新しい出会いと経験が、彼のこれからの成長に繋がることを、彼自身も少しずつ確信し始めていた。

文芸部での新しい出会い
須波くんは、初めて文芸部の部室に足を踏み入れた時のことを鮮明に覚えていた。放課後の静けさの中、部室の扉を開けると、温かい光が差し込む部屋には、すでに数人の部員たちが集まっていた。部長の安登先輩を始め、みんなが彼を笑顔で迎えてくれた。
「須波くん、ようこそ。座ってゆっくりしてね。」安登先輩の穏やかな声が彼を安心させた。
須波くんは、部室の一角にある大きなテーブルに腰を下ろし、周りを見渡した。壁には部員たちが書いた詩や短編小説が掲示され、書棚には文学作品がぎっしりと並んでいた。この場所が、これからの彼の活動の場となるのだと思うと、少しだけ胸が高鳴った。
「今日は特に課題はないから、自由に過ごしていいよ。何か書きたいことがあれば、どんどん書いてみて。」吉浦さんが優しく声をかけた。
須波くんは手元にノートを広げ、ペンを握りしめた。しかし、何を書けばいいのか全くわからなかった。頭の中にはいくつものアイデアが浮かんでは消えていく。そんな彼を見て、近くにいた部員の一人が話しかけてきた。
「初めてだと何を書けばいいか迷うよね。僕も最初はそうだったよ。」その部員、田中くんはにこやかに言った。「でも、自分が好きなことや感じたことを素直に書けばいいんだ。文芸部は誰かに評価される場所じゃなくて、自分を表現する場所だからさ。」
田中くんの言葉に励まされ、須波くんは少しだけ気持ちが軽くなった。彼は自分の中で感じていること、日常の些細な出来事を思い出しながら、ペンを動かし始めた。
時間が経つにつれ、須波くんは文芸部の雰囲気に次第に慣れていった。部員たちはそれぞれが自分のペースで作品を書き、時にはお互いに意見を交換し合ったり、アドバイスを送り合ったりしていた。その中には、詩を書くのが得意な佐藤さんや、ファンタジー小説を書いている山田さんもいた。
「須波くん、これ読んでみて。」佐藤さんが自分の書いた詩を見せてくれた。
「すごく素敵な詩だね。言葉の選び方がとても繊細で、心に響くよ。」須波くんは率直に感想を述べた。
「ありがとう。でも、もっと上手く書けるようになりたいんだ。だから、みんなの意見を聞くのは本当に参考になるんだよ。」佐藤さんは微笑んだ。
その後も、須波くんは部員たちとの交流を楽しみながら、自分のペースで文章を書き続けた。彼が感じたことや考えたことを素直に表現することの楽しさを再発見し、少しずつ自信を持ち始めた。
ある日、文芸部の活動が終わった後、安登先輩が須波くんに声をかけた。
「須波くん、君の書いた文章、すごく良かったよ。特に感情の描写が素晴らしいと思った。これからも続けて書いてみてほしいな。」
安登先輩の言葉に、須波くんは心から嬉しくなった。彼は、自分が書いたものが誰かに読まれ、評価されることの喜びを初めて感じたのだ。
「ありがとうございます。もっと頑張ります。」須波くんは力強く答えた。
文芸部での新しい出会いと経験が、須波くんにとって大きな財産となっていく。彼はこの場所で、自分の内面を見つめ直し、新しい自分を発見する旅を続けることになるだろう。その第一歩を踏み出した須波くんは、これからも成長し続けるに違いない。
須波くんの悩み
文芸部に入部して数週間が経った。須波くんは少しずつ部活動に慣れ、部員たちとの交流も増えてきた。しかし、彼の心の中には常に一つの悩みがあった。それは、自分の文章が本当に良いものなのかどうかという不安だった。
ある日の放課後、部室で須波くんは一人、ノートと向き合っていた。ペンを握りしめ、頭を悩ませながらも、思うように言葉が出てこない。そんな彼の様子を見ていた吉浦さんが、そっと近づいてきた。
「須波くん、最近元気ないみたいだけど、どうしたの?」吉浦さんは心配そうに尋ねた。
「実は…自分の文章に自信が持てなくて。みんなの作品と比べると、どうしても自分のが劣っているように感じるんだ。」須波くんは素直に打ち明けた。
「そうなんだ。でも、みんなも最初は同じように悩んでいたと思うよ。私も最初は全然自信がなくて、何度も書き直したりしてた。でも、大事なのは続けることだと思う。少しずつ自分のスタイルが見つかってくるから。」吉浦さんは優しく励ました。
須波くんは、その言葉に少しだけ救われた気がした。しかし、根本的な不安はまだ消えないままだった。その日の帰り道、彼は深く考え込んでいた。
次の日、文芸部の活動中、須波くんは安登先輩に声をかけられた。
「須波くん、少し話せるかな?」安登先輩は柔らかい笑顔で言った。
「はい、もちろん。」須波くんは少し緊張しながらも、先輩の後についていった。
安登先輩は部室の隅にあるソファに腰を下ろし、須波くんも隣に座った。部室は静かで、他の部員たちはそれぞれの活動に集中していた。
「最近、何か悩んでいることがあるんじゃないかと思ってね。もし良かったら話してくれる?」安登先輩は穏やかな声で尋ねた。
「実は、自分の文章に自信が持てなくて…。どうしても他の人の作品と比べてしまうんです。」須波くんは正直に打ち明けた。
「そうか。須波くんの気持ち、よくわかるよ。実は僕も昔、同じように悩んでいたんだ。」安登先輩は自分の経験を話し始めた。「でも、その時、ある先生に言われたことがあってね。『書くことは自分を表現する手段だ。他人と比べるのではなく、自分の感じたことや思ったことを素直に書けばいいんだよ』って。」
「それからは、自分の感じたことを大切にして書くようにしたんだ。もちろん、他の人の意見を聞くことも大切だけど、まずは自分の中の声に耳を傾けることが大事だと思う。」
須波くんは、安登先輩の言葉に深く考えさせられた。自分の感じたことや思ったことを素直に表現すること。それが本当に大切なことなのかもしれない。
「ありがとうございます、先輩。少し気持ちが楽になりました。これからは、自分の気持ちを大切にして書いてみます。」須波くんは感謝の気持ちを込めて答えた。
その日の帰り道、須波くんは空を見上げながら考えた。自分の文章に自信が持てなくても、それを通じて自分を表現することができるなら、それでいいのかもしれない。そして、少しずつでも成長していければ、それが本当の意味での進歩だと感じた。
翌日の文芸部の活動では、須波くんは新たな気持ちでノートに向かった。ペンを握りしめ、心の中で感じたことを素直に書き始めた。その言葉は、以前よりもずっと自然で、自分自身の気持ちをしっかりと表現していた。
須波くんの悩みは完全に解決したわけではないが、彼は新しい視点を持つことができた。そして、その視点が彼の成長を促し、文芸部での活動に新たな意味をもたらしたのだった。
安登先輩との対話
ある日の放課後、文芸部の部室に静寂が訪れていた。須波くんは机に向かってノートとペンを前にしていたが、その手は止まったままだった。自分の感じたことを素直に表現しようと努めてはいるものの、言葉がうまくつながらなかった。
その時、安登先輩が部室に入ってきた。彼は須波くんの様子を見て、何かを感じ取ったようだった。安登先輩は静かに近づき、隣の席に座った。
「須波くん、今日は何か悩んでるのかな?」安登先輩は穏やかな声で尋ねた。
「うん、ちょっとね。自分の文章がどうしても思うように書けなくて…。どうやって表現すればいいのか、迷ってしまうんだ。」須波くんは正直に答えた。
安登先輩は頷きながら、少し考え込んだ後、口を開いた。「僕も同じような経験をしたことがあるよ。書くことは難しいし、自分の思いを言葉にするのは簡単じゃない。でも、一つだけ大事なことがあると思うんだ。」
「それは何ですか?」須波くんは興味津々で尋ねた。
「それは、自分の心の声に耳を傾けることだよ。外の評価や他人の意見を気にしすぎると、本当に自分が伝えたいことが見えなくなってしまう。まずは自分の内側にある感情や思いをしっかりと感じ取って、それをそのまま表現することが大切だと思う。」
「心の声…」須波くんはその言葉を繰り返し、自分の中で咀嚼しようとした。
「そう。例えば、今日感じたことや、最近の出来事を思い出してみて。それを素直に言葉にするんだ。誰かに見せるためじゃなくて、自分のために書くんだよ。」安登先輩は優しく微笑んだ。
須波くんは安登先輩の言葉に励まされ、もう一度ノートに向かった。今日一日を振り返り、何を感じたかを素直に書き始めた。ペンが紙の上を滑る音が、静かな部室に響いた。
「例えば、最近の僕ならね…」安登先輩も自分のノートを開き、書き始めた。「こんな風に、心に浮かんだことをそのまま書いてみるんだ。」
須波くんは先輩の書く様子を見ながら、自分も同じように試みた。最初は言葉がなかなか出てこなかったが、少しずつ心の中にある思いが形になり始めた。
「どう?少し書けたかな?」安登先輩が尋ねた。
「うん、少しだけど、自分の思いが言葉になった気がする。」須波くんは少し恥ずかしそうに答えた。
「それでいいんだよ。最初は少しずつでいいんだ。大事なのは、続けること。続けていれば、必ず自分のスタイルが見つかるから。」安登先輩は励ますように言った。
その後も、須波くんは何度もノートに向かい、自分の思いを言葉にし続けた。少しずつではあるが、自信がついてきた。そして、安登先輩との対話を通じて、自分の心の声に耳を傾けることの大切さを学んだ。
ある日、須波くんは自分の書いた文章を安登先輩に見せた。「先輩、これ、読んでみてください。」
安登先輩は須波くんの文章をじっくりと読み、その後、にっこりと微笑んだ。「素晴らしいよ、須波くん。君の感じたことがしっかりと伝わってくる。これからも自分の心の声に耳を傾けて、書き続けてね。」
須波くんはその言葉に勇気をもらい、さらに一歩前進する決意を固めた。文芸部での経験は、彼にとって大きな成長の場となり、新たな挑戦への一歩を踏み出すきっかけとなったのだった。
新たな一歩
文芸部での活動が続く中、須波くんは少しずつ自信を取り戻していった。安登先輩や吉浦さん、そして他の部員たちとの交流を通じて、自分の文章が少しずつ形になっていくのを実感していた。そして、何よりも自分の感じたことを素直に表現することの楽しさを再発見していた。
ある日、文芸部のミーティングで部長の安登先輩が新しい提案を持ちかけた。
「みんな、ちょっと聞いてほしいんだけど、今度の文化祭で文芸部の作品展示をやろうと思ってるんだ。各自、自分の書いた作品を展示して、来場者に見てもらおうと思うんだけど、どうかな?」
部員たちはざわめきながらも、興味深そうにその提案を受け入れた。文化祭での展示は、自分たちの作品を広く公開する絶好の機会だ。しかし、それは同時に大きなプレッシャーでもあった。
須波くんも、その提案に心を揺さぶられた。自分の文章が他人に見られることに対する不安はあったが、同時にそれが成長のチャンスであることも理解していた。部員たちが次々と賛同の意を示す中、須波くんも小さく頷いた。
「僕も、挑戦してみます。」須波くんは決意を込めて言った。
文化祭に向けての準備が始まった。須波くんは自分の書いた作品を何度も読み返し、修正を重ねた。自分の思いをどう表現すればより伝わるか、何度も考え、試行錯誤を繰り返した。
そして迎えた文化祭当日。文芸部の展示ブースには、各部員が心を込めて作り上げた作品が並んでいた。須波くんの作品もその中にあり、緊張と期待が入り混じった気持ちで見守っていた。
展示が始まると、多くの来場者が足を止め、部員たちの作品に目を通していった。須波くんの作品の前にも、次々と人が立ち止まり、感想を述べてくれた。
「この文章、すごく心に響いたよ。」
「感情の描写がとても繊細で、引き込まれた。」
来場者たちの言葉に、須波くんは胸がいっぱいになった。自分の感じたこと、思ったことが他人に伝わり、共感を得ることができたという実感が湧いてきた。
展示が終わった後、部員たちはそれぞれの感想を共有し合った。みんなが互いの努力を称え合い、次のステップへ向けての意欲を新たにしていた。安登先輩も、満足そうに部員たちの成長を見守っていた。
「須波くん、素晴らしい展示だったね。」安登先輩が話しかけてきた。「君の作品は、多くの人に感動を与えたよ。この調子で、これからも自分の思いを大切にして書き続けてほしい。」
「ありがとうございます、先輩。これからも頑張ります。」須波くんは感謝の気持ちを込めて答えた。
文化祭での成功は、須波くんにとって大きな自信となった。そして、それは新たな挑戦への一歩でもあった。彼はこれからも文芸部での活動を続け、自分の表現を深めていくことを決意した。
その日の帰り道、須波くんは心の中で新たな目標を見つけた。自分の感じたことをもっと多くの人に伝えたい、もっと深く表現したい。そのために、もっと学び、もっと書き続けていこうと誓った。
文芸部での経験は、彼にとって大きな成長の場となり、新たな一歩を踏み出すきっかけとなった。須波くんは、自分の中にある無限の可能性を信じ、これからも前に進んでいくことを決めたのだった。

運動部しかない学校に存在する誰も知らない秘密の文芸部。
そこは表では健全なオタサーではあるものの、一つ扉を隔てた隣の部屋では大量のエロ漫画とおもちゃが置かれて部員達がお互いに性欲を思う存分発散し合う地味なオタク達のためのヤリサーだった…!
3人の地味な女子部員たちに経験豊富な顧問の先生も参加して文芸部の性活は更に盛り上がっていく…!◇放課後交尾〜1.5
吉浦さんに誘われ文芸部に入部したと同時に童貞を捨てた須波くん。
そんな次の日…前日の性臭が漂う部室で再び皆とセックスをしていると予期せぬ来訪者が…◇放課後交尾〜2
保健室に呼ばれた須波くんと安登先輩
部活の様子を聞いてみるとセックスの様子を配信したり女子更衣室に侵入したりとヤりたい放題。
そんな部活内容を聞いた先生も須波くんをつまみ食いしたくなり安登先輩を横目にベッドに連れて行き…
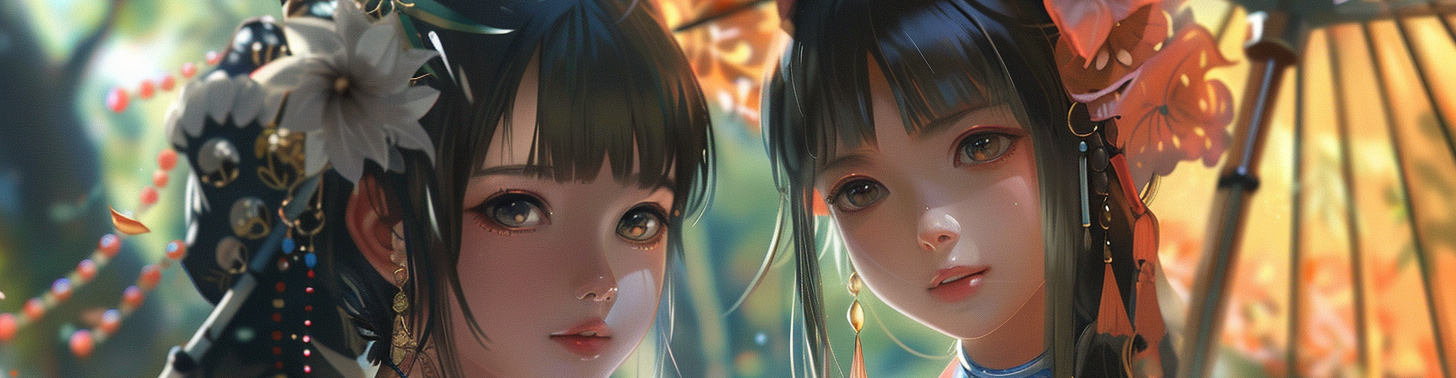


コメント