「男子禁制」の合宿に誤って参加することになった僕
僕の名前は山田太郎。高校2年生で、どちらかというと目立たない方だ。そんな僕が、まさか「男子禁制」の合宿に参加することになるなんて、誰が想像しただろうか。
事の始まりは、クラス委員の佐藤さんから届いたLINEだった。「来週の合宿の申込書、まだ出してないでしょ? 今日中に提出してね」。僕は慌てて教室に戻り、残っていた申込書に記入した。その時、誰も教室にいなかったことが、この珍事の伏線だったのかもしれない。
数日後、担任の先生から呼び出しを受けた。「山田くん、君、女子限定の合宽に申し込んでるけど…」。その瞬間、僕の頭の中が真っ白になった。よく見れば確かに、申込書の上部に「女子限定」の文字。どうやら、男子用と女子用の申込書が別々に用意されていて、僕は間違って女子用のものに記入してしまったらしい。
しかし、ここで思わぬ展開が待っていた。「実は、君が参加しないと最小催行人数に達しないんだ。何とか参加してもらえないかな?」先生の言葉に、僕は困惑した。でも、みんなの楽しみにしている合宿をキャンセルにするわけにはいかない。そう思った僕は、勇気を振り絞ってうなずいた。
次の日、クラスで合宿の説明会が開かれた。僕の参加が発表されると、教室中がざわめいた。女子たちの間から「エー!」という声が上がり、僕はその場に縮こまりそうになった。でも、佐藤さんが「太郎くんのおかげで合宿に行けるんだから、みんなで楽しもう!」と言ってくれて、少し救われた気がした。
それでも、女子たちの視線は冷ややかだった。「どうせモテないくせに」「きっと下心があるんでしょ」。そんな囁きが聞こえてきて、僕の心は沈んでいった。
合宿当日、バスに乗り込む時から、僕の居心地の悪さは最高潮に達した。誰も隣に座ろうとせず、結局最後尾の一人席に座ることに。3時間の長旅の間、僕はずっと窓の外を眺めていた。
宿に着いて部屋割りが発表された時、僕は別室を用意されていた。「山田くんは一人部屋ね」という先生の言葉に、僕は安堵と寂しさを同時に感じた。
夕食の時間、食堂は女子たちの賑やかな声で溢れていた。僕だけが一人、端の席で黙々と食事をする。「ここに来るべきじゃなかったかも」。そう思いながら、僕は明日からの日程表を眺めていた。
そんな僕の、予想外の合宽生活が始まったのだった。

女子たちの警戒心と僕の居場所のなさ
合宿2日目の朝、僕は重い足取りで食堂に向かった。昨夜の孤独な夕食の記憶が、まだ鮮明に残っている。食堂に入ると、すでに賑やかな女子たちの声で溢れていた。僕が入ってきたことに気づいた瞬間、その声は急に小さくなった。
「おはよう」と小さな声で挨拶をしたが、返事はまばらだった。テーブルに着くと、周りの女子たちがさっと距離を取る。その様子を見て、僕は胸が締め付けられる思いがした。
朝食を黙々と食べていると、隣のテーブルから聞こえてくる会話に耳を傾けてしまう。「ねえ、あいつってなんで来たの?」「きっと女子の水着姿が目当てでしょ」「気持ち悪い」。そんな言葉が、僕の心に突き刺さる。
食事を早々に切り上げ、一人で部屋に戻る。窓から外を眺めると、晴れ渡る空と輝く太陽が目に入る。本来なら、みんなで楽しむはずの天気なのに。
午前中のプログラムは、近くの森でのネイチャーゲーム。班ごとに分かれて行動するのだが、僕の班の女子たちは明らかに僕を避けている。「太郎くん、あっちの木を調べてきて」と、わざと離れた場所に行かせようとする。仕方なく言われた通りにするが、孤独感は増すばかりだった。
昼食時、食堂のテーブルで僕の隣の席が空いているのを見て、クラス委員の佐藤さんが近づいてきた。「ごめんね、みんな慣れてないだけだから」と、優しく声をかけてくれる。その言葉に少し救われた気がしたが、すぐに後ろから「佐藤さん、こっちおいでよ」という声がして、彼女は苦笑いを浮かべながら離れていった。
午後は、湖でのカヌー体験。準備体操の時、僕はグループの端っこに立っていた。インストラクターが「二人組になって」と言った瞬間、みんなが慌ただしくペアを作り始める。予想通り、僕には誰も近づいてこない。結局、先生が「山田くん、先生とペアになろう」と声をかけてくれた。
カヌーに乗り込む時、僕は一人で漕ぐことになった。湖面に映る自分の姿を見ながら、「なんでこんなことになったんだろう」と考え込んでしまう。周りでは女子たちの楽しそうな笑い声が響いているのに、僕だけが取り残されているような気分だった。
夕方、入浴の時間になった。当然、僕は一番最後の時間帯に割り当てられた。誰もいない浴室で、僕はぼんやりと湯船に浸かる。「明日からの3日間、このままでいいのかな」と、不安が頭をよぎる。
夜のミーティングでは、明日のプログラムについての説明があった。「明日は料理対決だ」と先生が言うと、女子たちから歓声が上がる。その中で、僕は「自分の出番はあるのだろうか」と不安になった。
就寝準備を終え、一人部屋のベッドに横たわる。天井を見つめながら、今日一日の出来事を振り返る。女子たちの警戒心、居場所のなさ、孤独感。でも、佐藤さんの優しい言葉を思い出すと、小さな希望も感じる。「明日こそは、何か変われるかもしれない」。そう思いながら、僕は目を閉じた。
意外な特技で女子たちの心を開く
合宿3日目の朝、僕は少し早起きをした。昨日までの孤独感を払拭したくて、何か自分にできることはないかと考えていた。食堂に向かう途中、ふと目に入ったのは、庭に咲く色とりどりの花々だった。
その時、僕の頭に一つのアイデアが浮かんだ。祖母が華道の先生をしていて、幼い頃からよく手伝いをしていたのだ。その経験を生かせるかもしれない。
食堂に入ると、いつもの冷ややかな空気が漂っていた。でも今日の僕は違う。「おはようございます」と、いつもより少し大きな声で挨拶をした。そして、勇気を出して提案した。「今日の料理対決で、料理の盛り付けを手伝わせてもらえませんか?」
最初は戸惑いの表情を浮かべていた女子たちだったが、クラス委員の佐藤さんが「いいじゃない、試してみよう」と後押ししてくれた。その言葉に、他の子たちも少しずつ頷き始めた。
料理対決が始まると、僕は各班を回って盛り付けのアドバイスをした。「この葉っぱをこう置くと、料理が引き立つよ」「器の向きを少し変えるだけで、印象が変わるんだ」。最初は遠慮がちだった女子たちも、僕のアドバイスを聞くうちに、少しずつ興味を示し始めた。
「ねえ、太郎くん、これどう思う?」「こっちの方がいいかな?」と、徐々に声をかけてくれる子が増えてきた。僕の存在が、少しずつ受け入れられていく感覚があった。
審査の時間。各班の料理が並べられると、先生たちから驚きの声が上がった。「今年は特に盛り付けが素晴らしいね」「見た目も味わいがあるわ」。女子たちの顔が、喜びで輝いていく。
結果発表。僕がアドバイスした班が1位と2位を独占した。歓声が上がる中、佐藤さんが僕に駆け寄ってきた。「太郎くん、ありがとう! みんな喜んでるよ」。その言葉に、僕の胸が温かくなった。
昼食時、雰囲気が一変していた。「太郎くん、こっちおいでよ」「盛り付けのこと、もっと教えてよ」。僕を呼ぶ声が、あちこちから聞こえてくる。戸惑いながらも、嬉しさで胸がいっぱいになった。
午後のプログラムは、キャンプファイヤーの準備。薪を積み上げる作業を手伝っていると、「太郎くん、そっちは危ないよ」と声をかけてくれる子がいた。その優しさに、僕は思わず笑顔になった。
夕方、キャンプファイヤーが始まった。炎が夜空に舞い上がる中、みんなで輪になって座る。すると、佐藤さんが立ち上がって言った。「今日は、太郎くんのおかげで素敵な思い出ができました。みんなで感謝の気持ちを込めて、拍手しましょう!」
突然の出来事に、僕は驚いて立ち尽くした。周りから大きな拍手が沸き起こる。照れくさくて顔が熱くなる。でも、この瞬間、僕はようやくこの合宿の一員になれたと実感した。
夜、一人部屋に戻った僕は、窓から見える星空を眺めながら、今日一日を振り返った。朝まで感じていた孤独感が、嘘のように消えていた。意外な形で、自分の居場所を見つけられたことに、心から感謝した。
明日からの残りの日程を思うと、少し胸が躍る。「きっと、もっと素敵な思い出が作れるはず」。そう思いながら、僕は穏やかな気持ちで眠りについた。
合宿のピンチを救う僕の活躍
合宿4日目、朝から晴れ渡る青空が広がっていた。今日のメインイベントは、近くの山でのハイキング。昨日の出来事以来、女子たちの態度が180度変わり、朝食時も僕を交えた楽しい会話で盛り上がっていた。
ハイキングが始まり、みんなで山道を登っていく。途中、珍しい植物を見つけては歓声を上げたり、景色のいい場所で写真を撮ったり。僕も自然と会話に加わり、楽しい時間が流れていった。
しかし、山頂に近づいたころ、突然の異変が起きた。空が急に暗くなり、遠くで雷鳴が聞こえ始めたのだ。先生が慌てて無線で天気を確認すると、予想外の雷雨が接近しているとのこと。「すぐに下山します!」という先生の声に、みんなの表情が一気に緊張に包まれた。
下山を始めて間もなく、雨が激しく降り出した。滑りやすくなった道を、みんな必死で歩いていく。そんな中、後ろの方で悲鳴が聞こえた。振り返ると、佐藤さんが足を滑らせて転んでしまったようだ。
僕はすぐに佐藤さんのところに駆け寄った。「大丈夫?」と声をかけると、彼女は顔をしかめながら「足首を捻ったみたい」と答えた。このまま放っておけば、全員の下山が遅れてしまう。
その時、僕は決断した。「佐藤さん、僕が背負って降りるよ」。周りから驚きの声が上がったが、今はそんなことを気にしている場合ではない。佐藤さんを背負い、慎重に一歩一歩、下山を続けた。
雨は一段と激しくなり、視界も悪くなってきた。それでも、僕は必死に前を見据えて歩き続けた。途中、道が分かりづらくなったとき、幼少期にボーイスカウトで学んだ知識を思い出した。「こっちの道の方が安全だと思います」と、先生に提案。先生も僕の判断を信頼してくれた。
1時間ほど歩き続けると、ようやく山の麓が見えてきた。全身びしょ濡れで疲れ切っていたが、みんなの無事な姿を確認すると、安堵の表情が広がった。
宿に戻ると、先生から僕に感謝の言葉があった。「山田くんの冷静な判断と行動のおかげで、全員が無事に下山できた。本当にありがとう」。その言葉に、周りの女子たちも口々に「ありがとう」「すごかったよ」と声をかけてくれた。
夕食時、いつもは賑やかな食堂が静かだった。みんな疲れ切っていたのだ。そんな中、佐藤さんが立ち上がって言った。「今日は太郎くんに助けてもらって、本当に感謝しています。私たちが最初、太郎くんを避けていたことを謝りたい」。その言葉に、他の子たちも頷きながら「ごめんね」「これからは仲良くしよう」と口々に言ってくれた。
僕は照れくさくて、うつむきながら「いや、僕こそみんなに助けてもらったよ。この合宿に参加できて本当によかった」と答えた。するとみんなから温かい拍手が沸き起こった。
その夜、一人部屋のベッドに横たわりながら、僕は今日の出来事を振り返った。危険な状況だったけれど、みんなで協力して乗り越えられたこと。そして、完全に仲間として認められたこと。この経験は、きっと一生の宝物になるだろう。明日は合宽最終日。どんな思い出で締めくくれるだろうか。そんなことを考えながら、僕は穏やかな気持ちで眠りについた。
仲間として認められ、忘れられない思い出を作る
合宿最終日の朝、僕は少し寂しい気持ちで目覚めた。昨日までの出来事が夢のように感じられ、この5日間があっという間に過ぎ去ってしまったことに気づいたからだ。
朝食の時間、食堂に入ると、みんなから明るい声で「おはよう、太郎くん!」と挨拶された。その瞬間、寂しさが消え、温かさに包まれる感覚があった。隣に座った佐藤さんが「太郎くん、今日は最後の日だね。楽しもう!」と笑顔で話しかけてくれた。
この日のプログラムは、合宿の思い出を形にするフォトコラージュ作り。グループに分かれて作業を始めたが、どのグループからも「太郎くん、この写真使っていい?」「この時の話、書いてよ」という声がかかった。自分がこんなにみんなの記憶に残っていたことに、胸が熱くなった。
昼食後、先生から驚きの発表があった。「みんなの要望で、最後にサプライズイベントを用意しました。湖でのカヌー大会です!」。歓声が上がる中、僕も心躍らせた。初日のカヌー体験で一人ぼっちだった記憶が、今はもう遠い過去のように感じられた。
カヌー大会が始まると、予想外の展開が待っていた。「太郎くん、一緒に漕ごう!」と、複数の女子から誘いを受けたのだ。結局、じゃんけんで決めることになり、僕は美咲さんとペアを組むことに。
レースが始まると、息の合った漕ぎで他のペアを次々と抜いていく。途中、バランスを崩して転覆しそうになった時も、お互いに声を掛け合いながら何とか持ちこたえた。最後の直線、僕たちは全力で漕ぎ、見事優勝を果たした。
湖畔に戻ると、みんなから祝福の声が上がった。「さすが太郎くん!」「美咲ちゃんとのコンビ最高だったよ!」。喜びを分かち合う中で、僕は心の底から幸せを感じていた。
夕方、閉会式が行われた。先生から「この5日間、みんなよく頑張りました。特に山田くんは、唯一の男子として大変だったと思いますが、最後には皆の心をつかみましたね」という言葉があった。そして、サプライズで「男泣き防止ハンカチ」という賞状と、みんなのメッセージが書かれたノートが贈られた。
僕は感極まって、言葉が出てこなかった。ただ、「みんな、ありがとう」と言うのが精一杯だった。すると、佐藤さんが「私たちこそ、太郎くんに感謝したい。この合宿を特別なものにしてくれてありがとう」と言ってくれた。その言葉に、他の女子たちも頷きながら拍手を送ってくれた。
夜、最後の夕食を食べながら、みんなで思い出話に花を咲かせた。笑いあり、涙ありの5日間を振り返る中で、僕は心からこの合宽に参加できて良かったと思った。
部屋に戻り、荷物をまとめながら、僕はもらったメッセージノートを開いた。一人一人の心のこもったメッセージに、またもや目頭が熱くなる。「明日からの学校生活が楽しみになったよ」「太郎くんのおかげで、男子の見方が変わったよ」。そんな言葉の数々に、この5日間の成長を実感した。
窓から見える満天の星空を眺めながら、僕は誓った。この合宿で得た絆と経験を大切にし、これからも周りの人々を大切にしていこうと。そして、いつか「男子禁制の合宿に男は僕一人」という珍事が起きたことを、笑い話として語れる日が来ることを願いながら、僕は静かに目を閉じた。
新たな絆を胸に、日常への帰還
合宿から一週間が経った月曜日、僕は少し緊張しながら教室のドアを開けた。合宿でのできごとが夢だったのではないかという不安が、心の片隅にあったからだ。
しかし、教室に一歩足を踏み入れた瞬間、その不安は吹き飛んだ。「おはよう、太郎くん!」と、いつもより明るい声で女子たちが挨拶してくれたのだ。男子たちは少し驚いた様子だったが、僕は嬉しさで胸がいっぱいになった。
休み時間、佐藤さんが僕の席に近づいてきた。「ねえ、太郎くん。合宿の写真、できたんだ。見る?」と言って、スマホの画面を見せてくれた。そこには、カヌーで優勝した時の写真や、フォトコラージュを作っている時の楽しそうな様子が映っていた。「みんなで見たいね」と佐藤さんが言うと、周りの女子たちも集まってきて、にぎやかに思い出話に花を咲かせた。
その様子を見ていた男子たちが、興味深そうに僕に声をかけてきた。「おい、山田。女子限定の合宿に行ったんだって?どんな感じだったんだ?」。僕は少し照れながらも、合宿での出来事を話し始めた。最初の居心地の悪さ、料理対決での盛り付けの成功、山でのハプニング、そして最後のカヌー大会のこと。話せば話すほど、男子たちの目が大きくなっていった。
「すげえな、山田!」「お前、一皮むけたんじゃねえか?」と、男子たちからも驚きと称賛の声が上がった。それを聞いた女子たちも「そうなの、太郎くんすごかったよ!」「最初は戸惑ったけど、今では太郎くんがいてよかったって思ってるの」と、口々に言ってくれた。
昼休み、いつもは男女で分かれて食べていた教室が、自然と一つの輪になっていた。合宿の話題から、学校生活の話、将来の夢の話へと、会話が弾んでいく。僕は、この自然な交流が生まれたことに、心から感謝した。
放課後、部活動の時間。僕は迷いながらも、華道部の門をたたいた。合宿で再認識した自分の特技を、もっと磨きたいと思ったからだ。「あら、山田くん。入部希望?」と顧問の先生が驚いた様子で迎えてくれた。部室に入ると、先輩たちも温かく迎えてくれ、早速基本から教えてもらうことになった。
その日の夕方、下校時に佐藤さんが声をかけてきた。「太郎くん、華道部に入ったんだって?すごいね!」。僕が頷くと、彼女は続けた。「実は私、お茶の稽古してるんだ。今度、お互いの活動について教え合おうよ」。僕は喜んで承諾した。
家に帰る道すがら、僕は空を見上げた。一週間前の自分には想像もつかなかった変化が、こんなにも自然に起きている。合宿で得た新しい絆が、日常生活を豊かなものに変えていることを実感した。
夜、日記を書きながら、僕は決意を新たにした。これからも、自分らしさを大切にしながら、周りの人々との絆を深めていこう。男女の壁を越えて、お互いを理解し合える関係を築いていこう。そして、あの「男子禁制の合宿に男は僕一人」という珍事が、かけがえのない経験として、これからの人生の糧になることを確信した。
明日はどんな出会いや発見があるだろう。そんな期待を胸に、僕は静かに目を閉じた。新しい日常の始まりを、心待ちにしながら。

童貞卒業を目標に入部したヤリサーの 「夏合宿」 を楽しみにしていた僕は
元陰キャな事がうっすらとバレており、夏合宿にむけた男部員だけでの飲み会に呼ばれていなかった。
ところがその飲み会で流行りの風邪が蔓延してしまったらしく、合宿にいける男部員は僕だけになってしまった!!!
当日、集合場所に現れたのは6人のサークルメンバーの女の子
なーんだ男コイツだけかよ…とがっかりされるが、
移動中の車内でズボンを脱がされるとチンコの大きさに目を輝かせる女子一同…!「これは期待できるね〜」「合宿中こいつで遊び倒そうぜ」
そんな感じで、ヤりまくりの合宿がはじまった!
ヒロイン全員にフェラされ、全員に挿入し、たっぷりパイズリシーンあり
楽しくエッチで幸せななハーレム本です。お楽しみください!
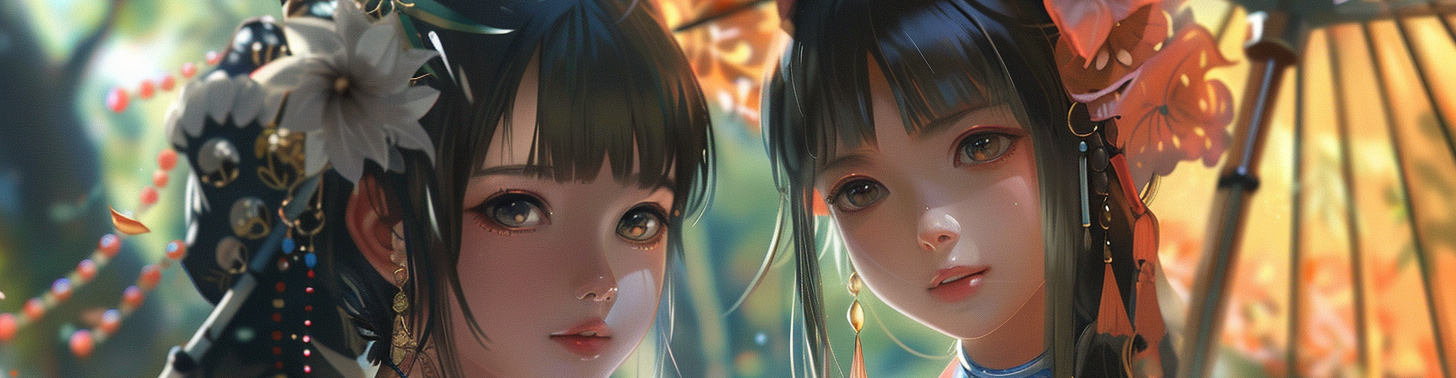


コメント